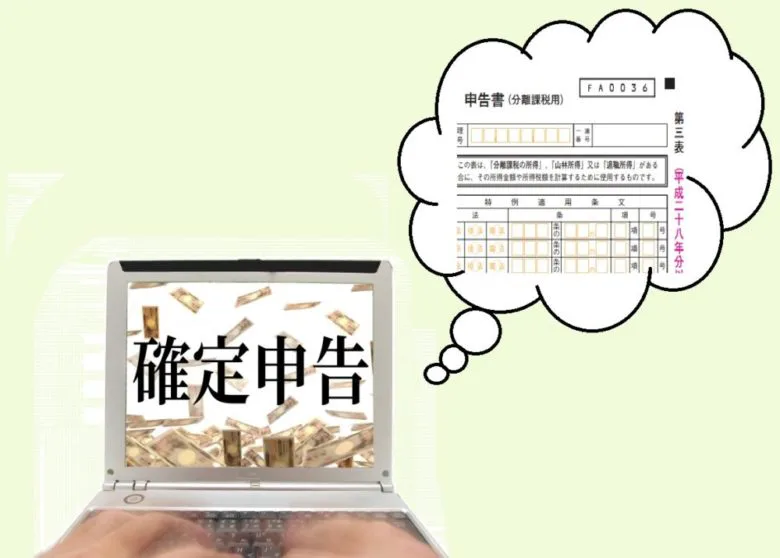
確定申告書【第三表】は何に使う?提出するケースや記入方法を再確認!

- 記事監修 大堀 優
-
税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
確定申告をする人なら誰もが手にする確定申告書。
ただし一口に確定申告書と言っても、あなたが確定申告する内容によって第一表から第五表まであります。
一般的によく利用するのは、第一表と第二表です。
しかし今回紹介するのは、第三表。
該当者はそこまで多くありませんが、その分いざ提出することになったとき、迷ってしまいがちです。
そこで本記事では次の3つの疑問を軸に紹介していきます。
- 確定申告の種類とは?
- 【第三表】の用途と該当する所得とは?
- 【第三表】の記入項目とは?
まずは“あなたは第三表を提出するべきなのか?”という点だけでも確認してみませんか?
- 目次
-
●疑問その1…まずはおさらい!確定申告書の種類一覧
確定申告書には第一表から第五表まであります。
それぞれどんな差異があるのか、下表でおさらいしておきましょう。
| 種類 | 主な内容 | 名称 | あわせて提出する書類 |
|---|---|---|---|
| 第一表 | 納税者の基本情報 収入、所得金額など税金の計算 |
確定申告書A 確定申告書B |
- |
| 第二表 | 第一表の明細 住民税や事業税に関する事項 |
確定申告書A 確定申告書B |
- |
| 第三表 | 分離課税対象の所得税など | 確定申告書(分離課税用) | 確定申告書B(第一表・第二表) |
| 第四表 | 損失申告対象の申告額など | 確定申告書(損失申告用) | 確定申告書B(第一表・第二表) |
| 第五表 | 修正申告する際の修正前の情報など | 修正申告書 | 確定申告書B(第一表) |
確定申告書AとBの違い
確定申告書AとBの違いは、確定申告する所得の種類によって異なります。
- 確定申告書A…「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」の4種のみ&予定納税がない場合
- 確定申告書B…全ての所得に利用可能
基本的には確定申告書Bを使うと考えて問題ありません。
確定申告書Aを使う主な例は、サラリーマンが会社で年末調整ができなかった次のような所得がある場合です。
- 生命・損害保険の一時金
- 公的年金
- 原稿料など多少の副収入
- 株式の配当金
●疑問その2…第三表は【分離課税】を申告するための書類!
確定申告書の概要がつかめたら、いよいよ確定申告書「第三表」について踏み込んでいきます。
結論から言うと、確定申告書の第三表は分離課税に該当する所得を申告する場合に利用します。
ここからは次のトピックを中心に確認していきましょう。
- 総合課税と分離課税について
- 申告分離課税に該当する所得
総合課税と分離課税について
確定申告をする際の課税方式には、
- 総合課税
- 分離課税
上記の2種類があります。
総合課税は対象の所得すべてを合計した金額が課税の対象となる課税方式です。
一方、分離課税は他の所得と一緒にせず、それぞれ個別に税率をかけて課税されます。
源泉? 申告? 【分離課税】は2種類アリ
分離課税にはさらに種類があることをご存知でしょうか?
- 源泉分離課税
- 申告分離課税
上記の2種類に分かれます。
源泉分離課税は分離課税対象の所得を、あらかじめ源泉徴収して受け取る方式のものです。
受け取った時点で税額分は差し引かれているので、とくに別途で確定申告をする必要はありません。
源泉分離課税に該当する所得の具体例は、以下に記載しています。
源泉分離課税の対象となる所得の具体例は、下記の抜粋を確認してみてくださいね。
(1) 利子所得に該当する利子等(総合課税又は申告分離課税の対象となるものを除く。)
(2) 私募の特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配
(3) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
(4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(5) 次の金融類似商品の補てん金等
イ 定期積金の給付補てん金
ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
ハ 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外国通貨に換算して支払うこととされている一定の換算差益
ヘ 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)
(6) 一定の割引債の償還差益
一方、申告分離課税はそれぞれ個別に税率をかけて課税額を割り出すので、確定申告が必須です。
以下では申告分離課税に該当する所得(=第三表に記載する所得)を1つずつ確認していきましょう。
申告分離課税に該当する7つの所得
申告分離課税に該当する所得は、主に次の7種類です。
- 譲渡所得
- 雑所得
- 山林所得
- 利子所得
- 上場株式配当所得(※選択制)
- 事業所得
- 退職所得
①:譲渡所得(株式、不動産など)
申告分離課税に該当する譲渡所得は、主に以下のような資産を譲渡した場合に発生します。
- 株式
- 不動産(土地・建物など)
- ゴルフ会員権
譲渡所得の計算方法は次のとおりです。
課税譲渡所得金額=収入金額 ー(取得費 + 譲渡費用)ー 特別控除額*
特別控除額は、下表のケースにより異なります。(最高限度額は5000万円)
| 譲渡ケース | 特別控除額 |
|---|---|
| 収用等(公共設備等)により譲渡 | 5000万円 |
| マイホームを譲渡 | 3000万円 |
| 特定土地区画整理事業等のために譲渡 | 2000万円 |
| 特定住宅地造成事業等のために譲渡 | 1000万円 |
| 2009年 or 2010年に取得した土地等を譲渡* | 1000万円 |
| 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡 | 800万円 |
*特別控除の対象となるのは、長期譲渡所得(=所有期間5年超の土地建物)の場合のみ。
税額は下記のように算出が可能です。(※)
- 長期譲渡所得(所有期間が5年超)…課税長期譲渡所得金額×15%
- 短期譲渡所得(所有期間が5年以下)…課税短期譲渡所得金額×30%
※2013年~2037年までは復興特別所得税として「各年の基準所得税額×2.1%」とあわせて申告・納付します。
②:雑所得(先物取引、FX取引など)
先物取引やFX取引等で生じた所得は「先物取引に係る雑所得等」として計上され、申告分離課税の対象となります。
先物取引とは「商品」「支払期日」「支払価格」を、あらかじめ決める取引のこと。
たとえば事前に「商品A」を「毎月20日」に「1万円」で購入するという取引が成立した場合…
- 「商品A」の価値が8000円になった
- 「商品A」の価値が1万2000円になった
上記のように購入時の価値が変動した場合でも、定額で「1万円」になります。
もし損失が出てしまった場合でも、「先物取引に係る雑所得等」同士(先物取引とFX取引など)でなら損益通算が可能です。
別の所得との損益通算はできないので、気をつけてくださいね。
また損失の度合いが大きくて1年間で控除しきれなかった場合は、翌年以後3年間にわたって繰越控除ができます。
③:山林所得
山林所得に計上される場合も、申告分離課税の対象です。
山林所得に該当する主なケースは、下記をご覧ください。
- 山林を伐採して譲渡する
- 立木(=地面に生えたまま)の状態で譲渡する
例外として、山林を山ごと譲渡した場合の土地は「譲渡所得」、山林の取得後5年以内の譲渡は「事業所得」として計上されるので、注意しましょう。
④:利子所得
- 預貯金
- 公社債の利子
- 合同運用信託
- 公社債投資信託
- 公募公社債等運用投資信託
上記のものは利子所得に含まれますが、源泉分離課税のため確定申告の対象ではありません。
ただし例外として、「2016/1/1以後に支払いを受ける特定公社債*等の利子等」については、申告分離課税の対象となります。
また申告分離課税の対象とはいえ、確定申告をしないという選択も可能です。
該当するのは、主に次のようなものです。
- 国債
- 地方債
- 外国国債
- 公募公社債
- 上場公社債
- 2015/12/31以前に発行された公社債
ちなみに利子所得には非課税制度が2つあります。
詳細は下記をご覧ください。
利子所得にある非課税制度は次の2種類。
- 障害者等の少額貯蓄非課税制度→最大350万円
- 勤労者財産形成住宅(or 年金)貯蓄の利子非課税制度→最大合計550万円
①の制度を利用できるのは…
- 国内に住所がある
- 身体障害者手帳の交付を受けている
- 遺族年金を受け取れる妻
上記のような一定の条件を満たした人に限ります。
②の制度も利用には、主に次のような条件をクリアしないといけません。
- 国内に住所がある
- 契約時の年齢55歳未満
- 勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出済み
*2013年~2037年までは復興特別所得税として「各年の基準所得税額×2.1%」とあわせて申告・納付するので、実際の税率は20.315%となります。
⑤:上場株式配当所得(※選択制)
上場株式配当所得の課税方式は…
- 総合課税
- 申告分離課税
上記のどちらかを選択できます。
ただし申告分離課税を選択した場合、配当控除を利用することはできません。
*2013年~2037年までは復興特別所得税として「各年の基準所得税額×2.1%」とあわせて申告・納付するので、実際の税率は20.315%となります。
⑥:事業所得
- 株式等を譲渡した際の所得
- 先物取引に係る所得
上記の所得を事業規模で得た場合は事業所得として計上され、申告分離課税の対象となります。
株式等の譲渡に係る主な具体例は、次のとおりです。
- 特定口座制度*
- 上場株式等に係る譲渡損失、配当所得等との損益通算
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定管理株式等が価値を失った場合の譲渡所得の課税の特例
- NISA(少額投資非課税制度)
- ジュニアNISA
*特定口座制度は証券会社等が上場株式等の譲渡損益を計算し、申告を簡易にする制度のこと。
*2013年~2037年までは復興特別所得税として「各年の基準所得税額×2.1%」とあわせて申告・納付するので、実際の税率は20.315%となります。
⑦:退職所得
退職時に発生する退職所得は源泉分離課税のため、原則として確定申告の必要はありません。
ただし例外として「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。
退職所得に該当するのは、主に次の3つです。
- 勤務先から受け取る退職手当
- 社会保険制度による退職一時金
- 生命保険会社 or 信託会社による退職一時金
退職所得控除額は、勤続年数によって異なります。
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円未満=80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
退職所得控除額を算出する際、以下のような条件がそろうと計算方法が異なります。
- 障害者になったことが原因で退職した…上記の表で算出後の金額+100万円
- 前年より前に退職金を受取済みである
- 同一年中に2箇所以上から退職金の受取がある
*2013年~2037年までは復興特別所得税として「各年の基準所得税額×2.1%」とあわせて申告・納付するので、実際の税率は20.42%となります。
●疑問その3…第三表【記入項目】を詳解!
ここからは。確定申告時に使用する確定申告書【第三表】の記入項目を確認していきましょう。
記入項目は大きく次の9つに分割しました。
- 基本情報 + 特例適用条文
- 収入金額
- 所得金額
- 税金の計算①
- 税金の計算②
- その他
- 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項
- 上場株式等の譲渡所得等に関する事項
- 分離課税の上場株式等の配当所得等に関する事項
- 退職所得に関する事項
また第三表の提出時には、あわせて確定申告書Bの「第一表」及び「第二表」の提出も必須なので、手元に用意しておくと記入がスムーズになります。
(画像引用元:申告書第三表(分離課税用)【令和元年分以降用】)
①:基本情報 + 特例適用条文
まず一番上の「○○申告書」の空欄のところには、「確定」と記入して、確定申告書であることを示します。
その次は基本情報として、「住所」「屋号」「氏名(フリガナ)」をそれぞれ記入しましょう。
そして問題が次の「特例適用条文」についてです。
ここには確定申告で利用する特例の根拠となる条文を記入します。
まずは次の3つの種類の法律から1つ選んでマルをつけてください。
- 所法(=所得税法)
- 所法58条(固定資産の交換の特例)など
- 措法(=租税特別措置法)
- 措法35条1項(居住用財産の譲渡の3000万円の特別控除の特例)
- 措法35条の2(特定の土地等を譲渡した場合の1000万円の特別控除)
- 措法39条(相続財産に係る譲渡所得の特例)など
- 震法(=震災特例法)
- 震法11条の6(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)など
上記で挙げた特例の具体例は一部なので、詳細は国税庁HPをご確認ください。
②:収入金額
収入金額の部分には、次の項目から該当する箇所に金額を記入していきましょう。
- 短期譲渡(一般分):シ
…所有期間が5年以内かつ通常の土地・建物を譲渡した場合
- 短期譲渡(軽減分):ス
…所有期間が5年以内かつ国・地方公共団体へ譲渡した場合
- 長期譲渡(一般分):セ
…所有期間が5年超かつ通常の土地・建物を譲渡した場合
- 長期譲渡(特定分):ソ
…所有期間が5年超かつ優良住宅地用の土地などを譲渡した場合
- 長期譲渡(軽課分):タ
…所有期間が10年超かつ居住用の財産を譲渡した場合
- 一般株式等の譲渡:チ
…非上場株式や私募株式投資信託の受益権などの株式を譲渡した場合
- 上場株式等の譲渡:ツ
…取引所に上場されている株式等を譲渡した場合
- 上場株式等の配当等:テ
…取引所に上場されている株式による配当等を受け取った場合
- 先物取引:ト
…先物取引による収入があった場合
- 山林:ナ
…山林や立木の譲渡があった場合
- 退職:ニ
…勤務先や保険会社等から退職金を受け取った場合
③:所得金額
所得金額の部分は収入金額と記入項目は一緒です。
ただし適用される控除などを加味した後の金額を記入するので、収入金額より金額は少なくなります。
また収入金額と所得金額で記入する項目は一致するはずなので、ズレがないか確認しておきましょう。
- 短期譲渡(一般分):59
- 短期譲渡(軽減分):60
- 長期譲渡(一般分):61
- 長期譲渡(特定分):62
- 長期譲渡(軽課分):63
- 一般株式等の譲渡:64
- 上場株式等の譲渡:65
- 上場株式等の配当等:66
- 先物取引:67
- 山林:68
- 退職:69
④:税金の計算 (1)
税金の計算の部分を記入時には、その名の通り計算しないと記入できない項目があるので、あらかじめ計算機を用意しておくとスムーズです。
- 総合課税の合計額:9
…確定申告書B「第一表」の⑨所得金額「合計」に記入した額を、転記します。
- 所得から差し引かれる金額:25
…確定申告書B「第一表」の㉕所得から差し引かれる金額「合計」に記入した額を、転記します。
- 課税される所得金額:70~77
…課税される所得金額の1つ目「⑨対応分:70」には、「総合課税の合計額:9」ー「所得から差し引かれる金額:25」を計算した額を記入します。
その他の対応分(71~77)については、「③:所得金額」の(59~69)で記入した項目の金額と対応しているところに、その分の金額を記入していってください。
⑤:税金の計算 (2)
【第三表】右上にある「税金の計算」には…
- 税額:78~85
- 税額の合計額:86
上記の2つを記入します。
税額:78~85
税額70~77対応分(78~85)に記入するのは、「総合課税」と「分離課税」2つの所得金額に対する税額です。
- 「総合課税」の所得金額に対する税額
…「④:税金の計算 (1)」で記入した「⑨対応分:70」× 所得税率 ー 控除額を計算した金額を記入します。
| 「⑨対応分:70」記入金額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000円~195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万超~330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
| 330万超~695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
| 695万超~900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
| 900万超~1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
| 1800万超~4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
| 4000万超 | 45% | 479万6000円 |
- 「分離課税」の所得金額に対する税額
…前提として分離課税に該当するのは「③:所得金額」で記入した「短期譲渡(一般分):59」~「先物取引:67」です。
その流れで「④:税金の計算 (1)」の「⑨対応分:70」~「69対応分:77」で記入した金額に税額をかけて記入しましょう。
税額の合計額:86
「税額:78~85」で記入した金額の合計額を記入します。
さらにその合計額は、確定申告書B「第一表:27」に転記してください。
⑥:その他
「その他」に記入するのは、損失に係る金額です。
次の3つの項目ごとに確認していきましょう。
- 株式等
- 配当等
- 先物取引
株式等
- 本年分の64、65から差し引く繰越損失額:87
「③:所得金額」で記入した本年分の「一般株式等の譲渡:64」「上場株式等の譲渡:65」から、差し引く繰越損失額を記入します。
- 翌年以後に繰り越される損失の金額:88
「一般株式等の譲渡:64」「上場株式等の譲渡:65」において、翌年以後に繰越す損失額を記入します。
配当等
- 本年分の66から差し引く繰越損失額:89
「③:所得金額」で記入した本年分の「上場株式等の配当等:66」で記入した額から、差し引く繰越損失額を記入します。
先物取引
- 本年分の67から差し引く繰越損失額:90
「③:所得金額」で記入した本年分の「先物取引:67」の額から、差し引く繰越損失額を記入します。
- 翌年以降に繰り越される損失の金額:91
「先物取引:67」において、翌年以後に繰越す損失額を記入します。
⑦:分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項
分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項には、以下の項目を記入していきます。
記入にあたって「譲渡所得の内訳書」から転記するものが多いので、あらかじめ作成してあると記入がスムーズです。
- 区分
「短期・一般」など、該当する譲渡所得の区分を記入します。
- 所得の生ずる場所
どこの土地・建物を譲渡したのかを記入します。(「譲渡所得の内訳書:2面(1)」から転記。)
- 必要経費
- 差引金額(収入金額―必要経費)
- 特別控除額
上記3つの金額は「譲渡所得の内訳書:3面(4)」から転記。
- 差引金額の合計額
- 特別控除額の合計額
それぞれ転記した額の合計額を記入しましょう。
⑧:上場株式等の譲渡所得等に関する事項
源泉徴収される特定口座を利用していて、年間を通して収入があった場合は、源泉徴収税額の合計額を記入します。
ちなみに専業主婦など扶養内で…
- 年間を通じてこの譲渡所得等のみ
- 基礎控除額の48万円以下
- 納税者本人の合計所得金額が2400万円以下
上記の条件を満たしたうえで確定申告をすると、源泉徴収税額の全額が還付されるのでオススメです。
⑨:分離課税の上場株式等の配当所得等に関する事項
この欄に記入する項目は、次の4つです。
あらかじめ「申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の記入を済ませておくと、スムーズに進みます。
また特定口座を所有している場合は、証券会社から「年間取引報告書」が送付されるので、そちらも参考にしてみてくださいね。
- 種目・所得の生ずる場所
…会社の株式なら「○○株式会社」など配当所得等が生じた場所を記入します。
(申告書付表「(2)本年分の損益通算前の分離課税配当所得等金額」から転記)
- 収入金額
…配当所得等の収入金額を記入します。
(申告書付表「(2)本年分の損益通算前の分離課税配当所得等金額の合計:a」から転記)
- 配当所得に係る負債の利子
…配当の元本を取得するために要した負債の利子の金額を記入します。
(申告書付表「(2)本年分の損益通算前の分離課税配当所得等金額の合計:b」から転記)
- 差引金額
…「収入金額」ー「配当所得に係る負債の利子」の金額を記入します。
⑩:退職所得に関する事項
この欄に記入するのは、次の3箇所です。
- 所得の生ずる場所
…退職所得を受け取った会社名(「○○株式会社」など)を記入します。
- 収入金額
退職金の額を記入します。
- 退職所得控除額
退職所得控除額を、勤続年数などを参考に記入します。(下表参照)
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円未満=80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
まとめ~申告期限が延長になっても油断は禁物!~
今回は確定申告書【第三表】について…
- 申告書の種類のおさらい
- 分離課税に該当する7つの所得
- 確定申告書【第三表】の記入項目の詳解
上記の項目を中心に解説してきました。
とくに確定申告書の記入項目は細かくて複雑なので、何も知らない状態で記入すると大幅な時間のロスに繋がります。
新型コロナウイルスの影響で、2019年度の申告期限は2020/4/16まで(※)と延長されたとはいえ、油断は禁物です。
※2020/4/6現在、4/17以降の申告も柔軟に対応するという発表がありました。詳しくは国税庁が発表したPDFをご覧ください。
「期限内に記入できる自信がない!」
「記入項目に漏れがないか不安だ…」
という想いを抱えている方は、いつでも弊所まで連絡してくださいね!
※第三表に該当するあなたの疑問をスパッと解決!

会社設立・創業支援なら、話しやすさNo.1のスタートアップ税理士法人にお任せください!
実績多数のスペシャリストが、会社設立に関するお問い合わせを幅広く受付中です。全国対応可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。























