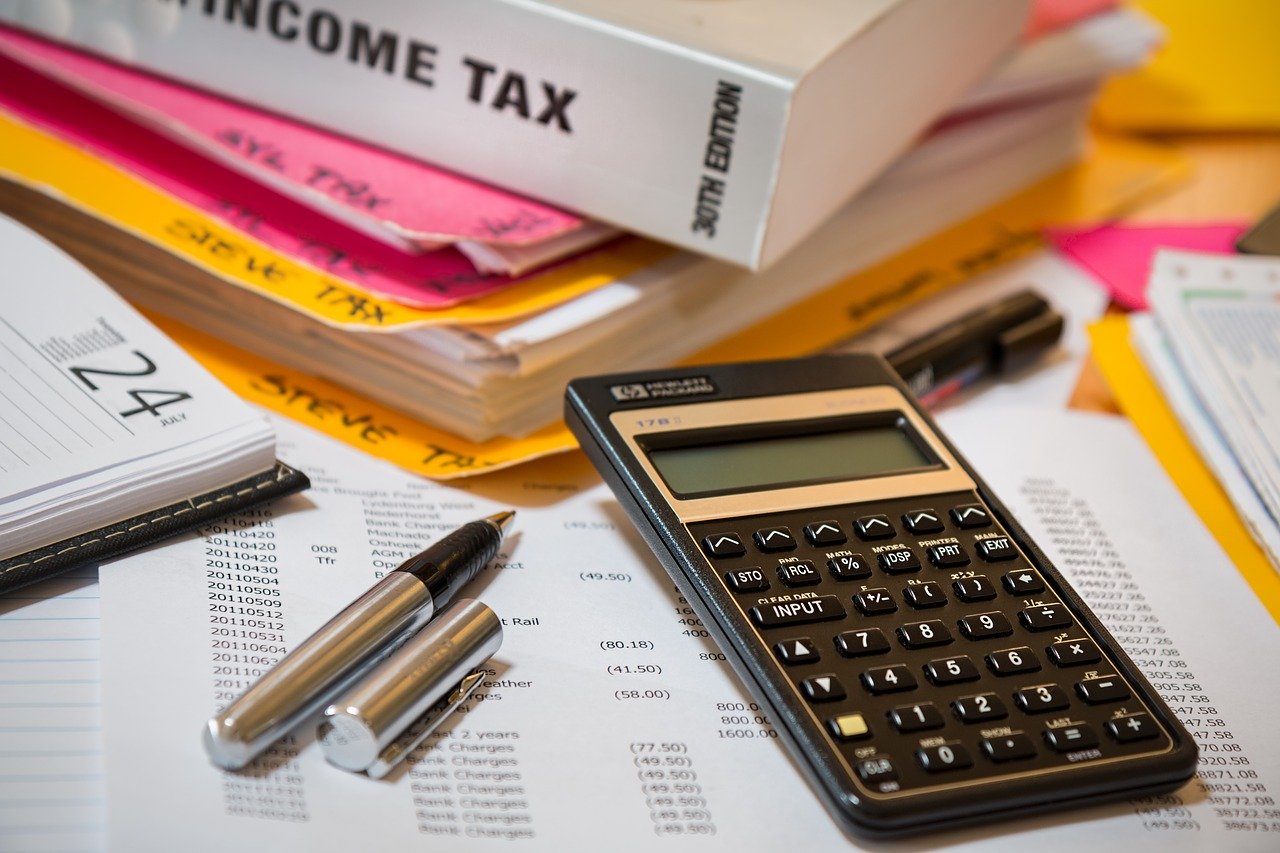
赤字でピンチの方必見【損益通算】で納税額を抑えませんか。

- 記事監修 大堀 優
-
税理士・大堀優(オオホリヒロシ)スタートアップ税理士法人代表。1983年、愛媛県出身。2013年に税理士登録をした後、2015年2月に独立開業しスタートアップ会計事務所を設立。 2017年1月、社会保険労務士事務所を併設する。2021年6月に会計事務所を税理士法人化、8月に横浜オフィスを開設。2023年4月に銀座オフィスを開設。
【会社設立をしたい方へ一言】みなさんの不安を払拭できるように、“話しやすさNo.1の事務所”として寄り添ったサポートを心掛けています。なんでもお気軽にご相談ください!
個人事業主の方は、確定申告の説明で「損益通算」を聞いたことがある方も多いでしょう。
損益通算は、“損失”が出ていない限り、利用することはありません。
そのため実際に”損失”が出たときに「損益通算」に手がつけられないという事態もありえます。
当記事で下記3点を確認し、納税額を少しでも抑えられるように、“損失”を活用する「損益通算」に取り組んでみませんか。
- 【損益通算】を理解するための前提知識
- 【損益通算】とは?
- 【損益通算】のやり方・順序
- 目次
-
「損益通算」を理解するための前提知識4点
「損益通算」をよりよく理解するためには、下記4点を確認しておく必要があります。
- 所得の種類は10種類
- 「総合課税」と「分離課税」
- 「申告分離課税」と「源泉分離課税」
- 「経常所得」と「非経常所得」
この4点の意味を確認しておけば、実際に損益計算の説明を読む際につまづかずに済むはずです。
①:所得の種類は10種類
所得はどのようにその収入を得たかによって、下記10項目の所得に分類されます。
その10種類の所得を合計した金額、もしくは個々に税率をかけて求められるのが、所得税額です。
そして「損益通算」が利用できるのは、この10種類の所得で赤字と黒字の両方が出たとき。
ただし所得の種類によっては、「損益通算」できないものもあり、その点は下記にて説明します。
| 不動産所得 | 配当所得 |
| 事業所得 | 給与所得 |
| 譲渡所得 | 退職所得 |
| 山林所得 | 一時所得 |
| 利子所得 | 雑所得 |
②:「総合課税」と「分離課税」
「総合課税」と「分離課税」は、所得税額の課税方法の区分です。
「損益通算」の計算で必要になると共に、申告書第三表・第四表を作成する際にも役立ちます。
- 「総合課税」…総合課税の対象所得を合計して税額を計算・課税する方法
- 「分離課税」…分離課税の対象所得は、個別に税額を計算・課税する方法
「総合課税」
総合課税の対象所得は、以下8点です。
| 総合所得 | 備考 |
| 利子所得 |
・源泉分離課税の対象 ・平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき特定公社債等*の利子等 上記2つを除く。 |
| 配当所得 |
・源泉分離課税の対象 ・確定申告しないもの ・平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したもの 上記3つを除く。 |
| 不動産所得 | ー |
| 事業所得 | 株式等の譲渡による事業所得を除く。 |
| 給与所得 | ー |
| 譲渡所得 | 土地・建物等・株式等の譲渡による譲渡所得を除く。 |
| 一時所得 | 源泉分離課税の対象を除く。 |
| 雑所得 |
・株式等の譲渡による雑所得 ・源泉分離課税の対象 上記2つを除く。 |
ちなみに一定の先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得は、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。
(参考:国税庁/「総合課税制度」)
特定公社債等とは、国際、地方債、外国国際、外国地方債、公募公社債、上場公社債などの一定の公社債や公社債投資信託のこと。
利子所得は、その支払いを受ける時に利子所得にかかる所得税が源泉徴収されるのが一般的です。
平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき特定公社債等については、次のような課税方法が取られています。
- 通常の利子所得のように源泉徴収される
- 申告分離課税の対象とし、自ら申告・納付する
確定申告をしないという選択もできますが、確定申告をしていずれかを選んだ場合、後に変更はできません。
ステップ1:総合課税の対象所得を合計する
→利子所得+配当所得+事業所得=合計額
ステップ2:合計した総所得金額から、所得控除を控除する
→合計額(=総所得金額)ー所得控除=所得
ステップ3:速算表を見て、所得金額から税率を決める
→所得金額が250万円→税率10%
ステップ4:所得金額にその税率をかける
→所得金額×10%=OOO円
ステップ5:算出された金額から税率に対応する控除額を差し引く
→OOO円ー控除額=納税額
| 所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万~330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万~695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万~900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万~1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万~4000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
「分離課税」
分離課税の対象所得は7つありますが、その7つは以下2つの納税方法に区分されています。
- 申告分離課税
- 源泉分離課税
そのためこれら2つについて説明する際に、どのような所得が対象になるのか確認してみましょう。
③:「申告分離課税」と「源泉分離課税」
「申告分離課税」と「源泉分離課税」は、分離課税の納税方法の区分です。
- 「申告分離課税」…自ら確定申告することで所得税を納める方法
- 「源泉分離課税」…所得になる収入を支払う会社が源泉徴収して代わりに所得税を納める方法
「申告分離課税」
申告分離課税の対象は以下7点です。
- 譲渡所得
- 雑所得
- 山林所得
- 利子所得
- 上場株式配当所得(※選択制)
- 事業所得(※条件アリ)
- 退職所得
「源泉分離課税」
源泉分離課税の対象となるのは、主に以下のようなものです。
(1)利子所得に該当する利子等(総合課税・申告分離課税の対象となるものは除く。)
(2)私募の特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
(3)私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
(4)懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(5)次の金融類似商品の補てん金等
イ 定期積金の給付補てん金等
ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
ハ 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
二 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円・他の外国通貨に換算して支払うこととされている一定の換算差益
へ 一時払養老保険・一時払損害保険などの差益(保険や共済の機関が5年以下・保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)
(6)一定の割引債の償還差益
(引用:国税庁/「No.2230 源泉分離課税制度」)
源泉分離課税の対象となる所得は、すでに税金が源泉徴収・納付されているため、計算方法は省略します。
| 単語 | 意味 |
| 私募 | 50人未満の投資家・銀行や保険会社などの金融機関や一定の要件を満たす法人などの「適格機関投資家」と呼ばれる“プロの機関投資家”を対象に勧誘すること。 |
| 特定目的信託 | 資産の流動化(資産を元手に資金調達すること)を目的とする信託。 |
| 社債的受益権 | 社債の利子のように、あらかじめ定められた金額の分配を受けられる権利。 |
| 公社債等運用投資信託 | 公社債、手形、債権者が特定している債権・合同運用信託に対する投資を運用する手段。 |
|
銀行法第2条第4項 |
この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。 (引用:電子政府の総合窓口e-Gov/「銀行法 施行日:平成29年4月1日)」 |
| 抵当証券 | 不動産を担保とした貸付債権(貸付金を返還してもらうための権利)の金額を少額にして、有価証券にしたもの |
| 売戻し条件付売買 | 将来のいつかに売り戻すことを条件に、購入する取引のこと。 |
④:「経常所得」と「非経常所得」
「経常所得」と「非経常所得」の区分は、「損益通算」の順序を理解する際に必要です。
| 概要 | 所得の種類 | |
| 経常所得 | 1年間、定期的に収入が得られる所得 |
利子所得、配当所得、不動産所得 事業所得、給与所得、雑所得 |
| 非経常所得 | 不定期・突発的に収入が得られる所得 | 一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得 |
「損益通算」とは?
「損益通算」とは上記で説明した10個の所得のうち、複数の所得を得ている方で
- 黒字の所得
- 赤字の所得
どちらもある場合に「損益通算」できる赤字の所得と、他の黒字の所得を相殺することを指します。
それぞれの所得金額を算出して、損益通算できる所得が赤字だった場合は、所得金額を減らすことが可能です。
所得金額に所得税率をかけて所得税額を求めるので、所得金額が減れば、必然的に納税額も減少。
もし損益通算できる損失があるのにスルーしていると、節税チャンスを逃したと考えられます。
「損益通算」できる所得
「損益通算」できる所得は、以下4点です。
- 不動産所得…土地・建物などの貸付けによる収入
- 事業所得…事業から得た収入
- 山林所得…取得してから5年を超えた山林を売却して得た収入
- 譲渡所得…ゴルフ会員権、船舶、機械などを譲渡して得た収入
この4つの所得が赤字だった場合に限り、他の黒字の所得と損益通算ができます。
【例外】損益通算できない
上記4つの所得に該当していても、下記のように「損益通算」できない損失もあるので、ご注意ください。
- 生活に通常必要でない資産の譲渡により生じた損失(例:競走馬、ゴルフ会員権、骨とう品など)
- 生活に必要な動産を譲渡して生じた損失(例:家具、衣服、貴金属など1個・1組の価額が30万円未満のもの)
- 個人に対して資産を低額で譲渡したことにより生じた損失
- 申告分離課税の対象となる譲渡所得(土地建物など)の計算上生じた損失(特例①)
- 株式等の譲渡により生じた損失(特例②)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失(特例③)
- 不動産所得の計算上生じた損失のうち、下記に該当するもの
たとえば生活に必要な動産を譲渡して得た収入は、非課税所得に該当するため、税金の計算上なかったものとみなします。
このように上記の損失はすべて、税金の計算上なかったものとみなすため、損益通算はできません。
ただし特例によって、認められる損失もあるので、確認しておきましょう。
損益通算できない不動産所得の計算上生じた損失は、以下3点です。
- 通常必要でない趣味、娯楽、鑑賞の目的で所有する不動産に係る損失(別荘など)
- 土地等を取得するための借入金の利子
- 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
ちなみに居住用以外の不動産を譲渡して生じた損失は、同じ条件の譲渡所得以外の他の所得とは損益通算できません。
まず組合契約とは、団体を作ることを合意し、共同の事業を営むために出資・労務の提供をする契約のこと。
これから説明する2点が損益通算できない所得に該当する条件に当てはまっていると、損益通算できません。
1つ目は、あなたが属している組合が下記のいずれかに該当する場合です。
- 民法上の組合契約(任意組合)
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合契約
- 外国におけるこれらに類する契約
また税務上、受益者等課税信託*として取り扱われるすべての信託経由で行った事業も該当します。
2つ目は、あなたが組合において下記のような立場の「特定組合員」に該当し、損益通算はできません。
組合契約を締結している組合員のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。
(引用(一部抜粋):電子政府の総合窓口/「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」)
受益者等課税信託*…受益者(=権利を現に有するもの)に発生時、課税される信託。たとえば、信託をしている人(受益者)がその信託などによる財産を有しているとみなして、そこから生じた収益も、信託をしている人に課税されます。
特例①:マイホームに関する特例
以下に該当する方で一定の条件に当てはまった方は、下記特例を利用しましょう。
- 居住用財産を買い替えた方
- 居住用財産を譲渡した方
そしてこの特例を利用すると、マイホームの買換え・譲渡により生じた損失を他の所得と損益通算できます。
あなたが利用できるのは「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
この特例は、令和元年12月31日までにマイホームを売却・購入し、売却の際に生じた損失が一定の要件を満たすと適用できます。
そしてこの特例が適用できると、損益通算が可能となるので、要件を確認しておきましょう。
- 自分が住んでいるマイホームを譲渡すること
- 譲渡する年の1月1日において、マイホームの所有期間が5年を超えること
- 災害に遭った家屋を所有・②に該当する場合、その災害があった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること
- 譲渡の年の前年1月1日~売却の年の翌年12月31日までに、日本国内の床面積50㎡以上の家屋を取得すること
- 新しくマイホームを購入した年の翌年12月31日までに居住のために利用・その見込みがあること
- 新しくマイホームを購入した年の12月31日に、そのマイホームの償却期間10年以上の住宅ローンがあること
より詳しい内容は、国税庁のHP「No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき」にてご確認ください。
あなたは「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用できるかもしれません。
この特例は、平成16年1月1日~令和元年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを売却して生じた損失が、一定の要件を満たすと適用できます。
下記の要件に当てはまっていると、損益通算できるので、ぜひ要件を確認してみてくださいね。
- 自分の住んでいるマイホームを譲渡すること
- 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超える、日本国内にあるマイホームの譲渡であること
- 災害に遭った家屋を所有・譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超える家屋の場合、その災害があった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること
- マイホームの売却契約日の前日に、そのマイホームに償却期間10年以上の住宅ローン残高があること
- マイホームの譲渡価額が④の住宅ローン残高より低いこと
より詳しい内容は、国税庁のHP「No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失」にてご確認ください。
特例②:上場株式等に関する特例
上場株式等*の配当を受けていて、金融商品取引業者等を通じて上場株式等の譲渡をした際に損失が生じた方は、以下の特例を利用しましょう。
「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を利用すると、上場株式等に関する下記2つを損益通算できます。
- 譲渡損失
- 配当所得(申告分離課税に限る)
この特例を利用できる上場株式等は、以下5つを含め20種類ほどあります。
- 金融商品取引所に上場されている株式等
- 日本銀行出資証券
- 外国金融商品市場において売買されている株式等
- 公募投資信託の受益権
- 国債及び地方債
上場株式等に該当する他の上場株式等は、国税庁/「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」にて、ご確認ください。
配当所得の申告方法を申告分離課税にすると、総合課税だと受けられる「配当控除」が受けられません。
「配当控除」とこの特例のどちらを受けた方が節税になるのか、あらかじめ調べておくことをオススメします。
税理士などの専門家に税額の計算を依頼し、金額を出してもらってから選択するのも手です。
特定口座とは、金融商品取引業者などに開設する口座のことです。
この口座を利用する際、源泉徴収の「あり・なし」を選択できますが、オススメは「源泉徴収あり」。
なぜなら「源泉徴収あり」を選択すると、下記の取引により生じた所得の損益通算・申告を金融商品取引業者が行ってくれるからです。
- 上場株式等の譲渡
- 上場株式等の利子・配当の受取
つまり特定口座(源泉徴収あり)を利用した場合、あなたは確定申告をする必要がありません。
ただし下記に該当する場合は、別途確定申告が必要なので、忘れないように気を付けましょう。
- 特定口座以外で取引した上場株式等がある
- 特定口座(源泉徴収なし)を選択した
特例③:先物取引に関する特例
先物取引の差金決済により損失が生じた場合は「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」を利用しましょう。
これを利用すると、先物取引を差金決済した場合に生じる所得の損益通算が認められます。
先物取引とは、将来いつの時点で、なにかをいくらで買う・売る契約をする取引のこと。
以下の例は、商品の受け渡しのある先物取引です。
A田さんは、1週間後の火曜日にダイヤモンドを5万円で購入する契約をB山さんと結びました。
そして1週間後のダイヤモンドの価額が7万円に上昇。
B山さんは2万円の損失を被りましたが、A田さんは2万円安く購入できました。
ただし今回の特例では、商品の受け渡しのない差金決済に限り適用できます。
差金決済とは、契約した金額(5万円)と1週間後の価額(7万円)の差額2万円を授受する決済方法のことです。
特例を利用できる先物取引は限られているので、利用できるか下記で確認しておきましょう。
特例を利用できる先物取引は、以下2点のうち下記条件に該当するものです。
- 商品の受け渡しがない商品先物取引
| 概要 | 具体例 |
| 平成13年4月1日以後に行う、商品先物取引法第2条*第3項に定められている先物取引で同項第1号から第4号までに掲げる取引のうち一定のもの |
|
| 平成24年1月1日以後に行う、商品先物取引法第2条*第14項に定められている店頭商品デリバティブ取引で同項第1号から第5号までに掲げる取引のうち一定のもの |
|
商品先物取引法第2条…電子政府の総合窓口e-Gov/「商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)」をご参照ください。
- 金融商品の受け渡しがない金融商品先物取引
| 概要 | 具体例 |
| 金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引のうち一定のもの |
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次の取引)
|
| 平成24年1月1日以後に行う、金融商品取引法第2条*第22項に定められている店頭デリバティブ取引で同項第1号から第4号までに掲げる取引のうち一定のもの |
|
金融商品取引法第2条*…電子政府の総合窓口e-Gov/「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)」にてご確認ください。
(引用:国税庁HP/「商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)」)
「損益通算」の順序
損益通算ができる損失があった方は、損益通算していく順序を確認していきましょう。
損益通算は、以下の5ステップで行います。
- 「利子・配当・給与・雑」ー「不動産・事業」
- 「一時」―「譲渡」
- ①ー② or ②-①
- 「山林」ー③
- 「退職」ー④
①:「利子・配当・給与・雑」ー「不動産・事業」
1つ目のステップでは、「経常所得」である「利子、配当、給与、雑、不動産、事業」の所得内で計算。
経常所得の中で損益通算ができるのは、「不動産・事業」に損失があった場合のみです。
その際は「利子・配当・給与・雑」の利益から「不動産・事業」の損失を差し引きます。
「利子・配当・給与・雑」ー「不動産・事業」
「利益 500万円」ー「損失 400万円」=「利益 100万円」
②:「一時」ー「譲渡」
2つ目のステップでは、非経常所得のうち「一時」と「譲渡」で計算。
損益通算できるのは「譲渡」が損失だった時のみなので「一時」の利益から「譲渡」の損失を差し引きます。
「一時」ー「譲渡」
「なし」ー「損失 300万円」=「損失 300万円」
③:①-② or ②-①
①の経常所得と②非経常所得において、どちらかが損失だった場合、損益通算できます。
①ー②(逆の場合もあり)
「利益 100万円」ー「損失 300万円」=「損失 200万円」
④:「山林」ー③
③をしても控除しきれない損失がある場合は、山林所得の利益から差し引きます。
「山林」ー③
「利益 100万円」ー「損失 200万円」=「損失 100万円」
山林所得が赤字の場合は、損益通算の順序が少し異なり、下記の順番に損益通算していきます。
- 経常所得:「利子・配当・給与・雑」ー「不動産・事業」ー「山林」
- 譲渡所得:「譲渡」ー①
- 一時所得:「一時」ー②
- 退職所得:「退職」ー③
⑤:「退職」ー④
④でも控除しきれない損失がある場合は、退職所得から差し引きます。
「退職」ー④
「利益 200万円」ー「損失 100万円 」=「利益 100万円」
実際に損益通算をした方の中には「計算後の金額を書けばいいんだ。」と思っている方もいるかもしれません。
しかし損益通算をした時の申告書Bの記載方法は、国税庁により定められています。
その詳しい方法は、国税庁/「損益通算を行う場合の申告書の記載要領」をご覧ください。
“損”した分「損益通算」で、納税額を少しでも抑えましょう。
今回は「損益通算」について、以下の順に説明してきました。
- よりよく理解するために必要な知識
- 損益通算とはなにか
- 損益通算のやり方
「損益通算」は納める税金を抑える効果があるので、損失のある方は損益通算ができる所得に該当するか、ぜひご確認ください。
所得が複数あると、損益通算の計算がとても複雑になります。
そのせいで下記のような疑問が生じたら、税理士などの専門家に正確な金額を出してもらうといいでしょう。
- 計算した金額が正しいのか
- 損益通算した方が納税額を抑えられるのか
そしてその金額を見て、本当に納税額を抑えられたか確かめてみてくださいね。
※下記フォームからのお問い合わせが、節税への近道!

会社設立・創業支援なら、話しやすさNo.1のスタートアップ税理士法人にお任せください!
実績多数のスペシャリストが、会社設立に関するお問い合わせを幅広く受付中です。全国対応可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

